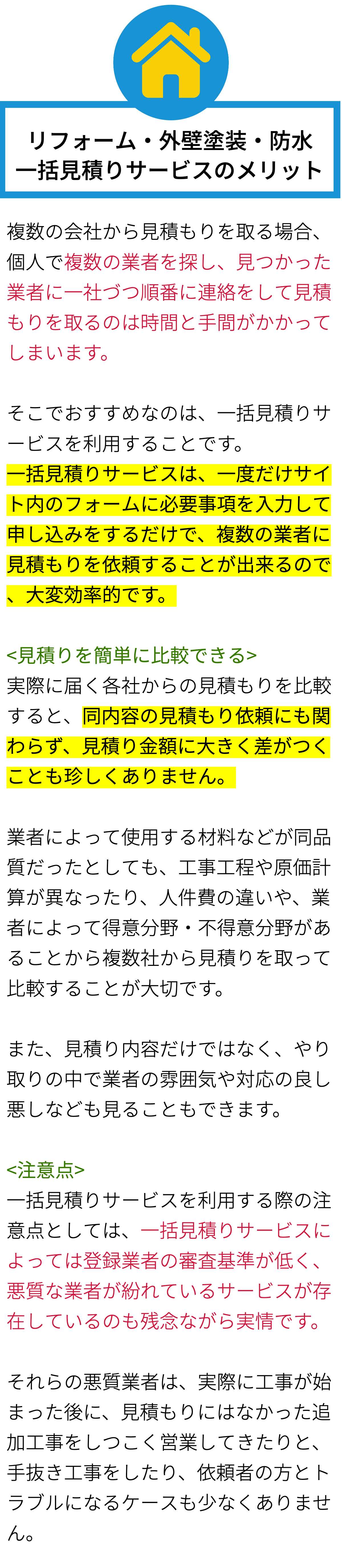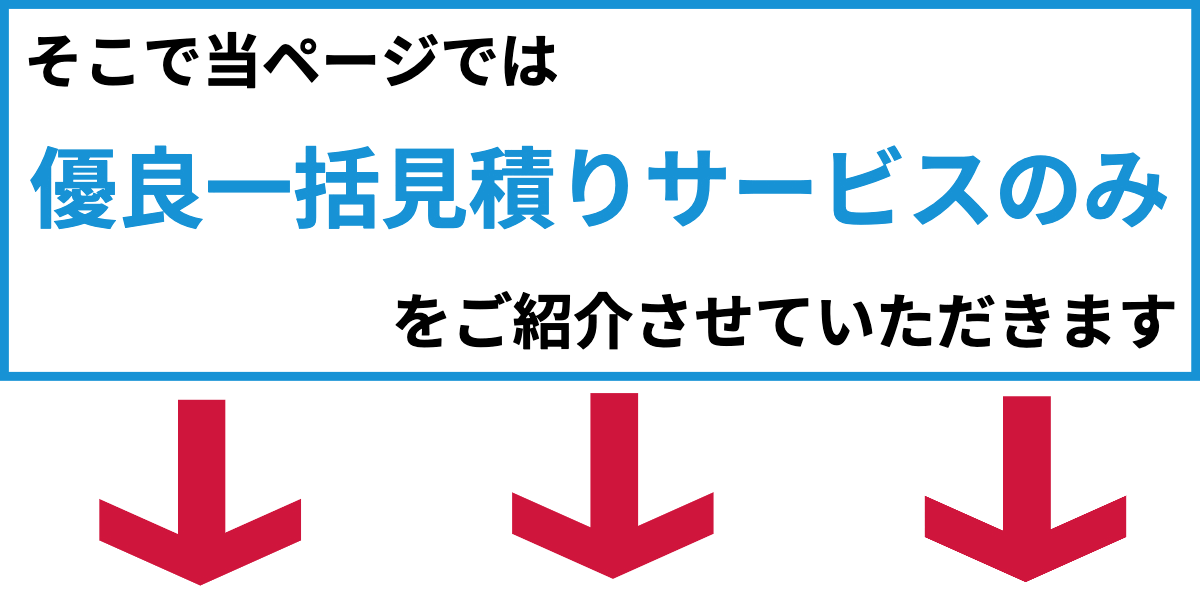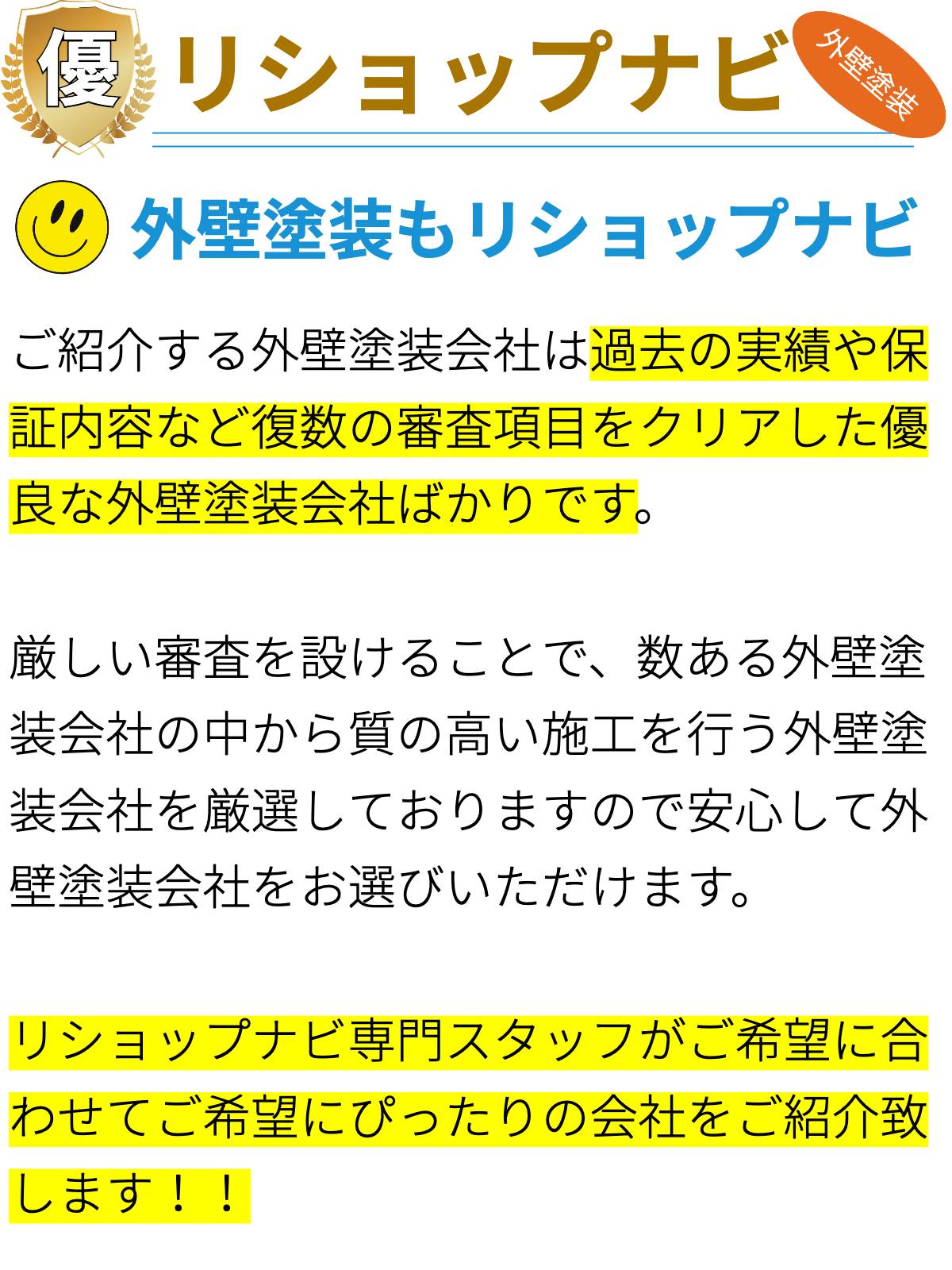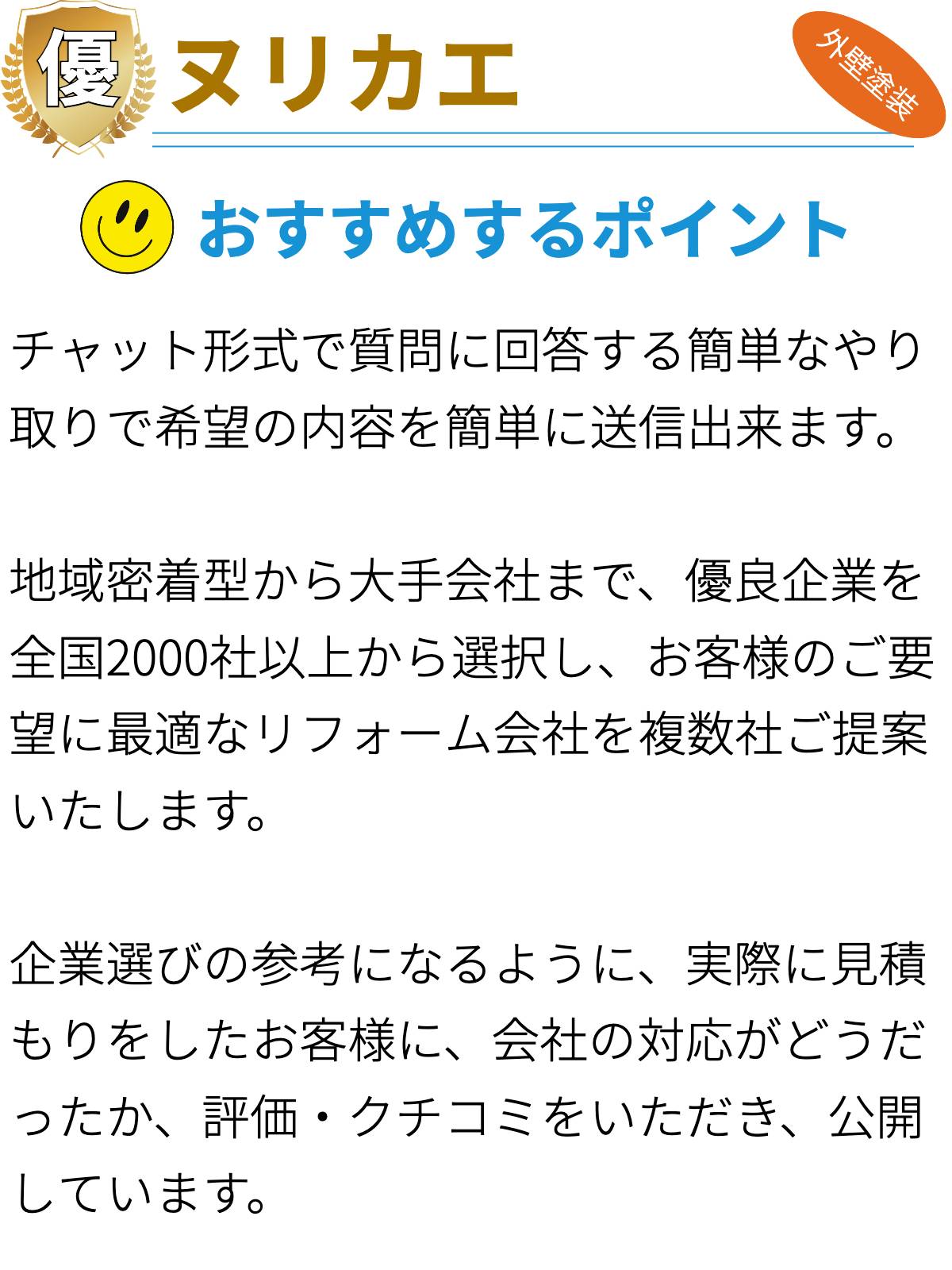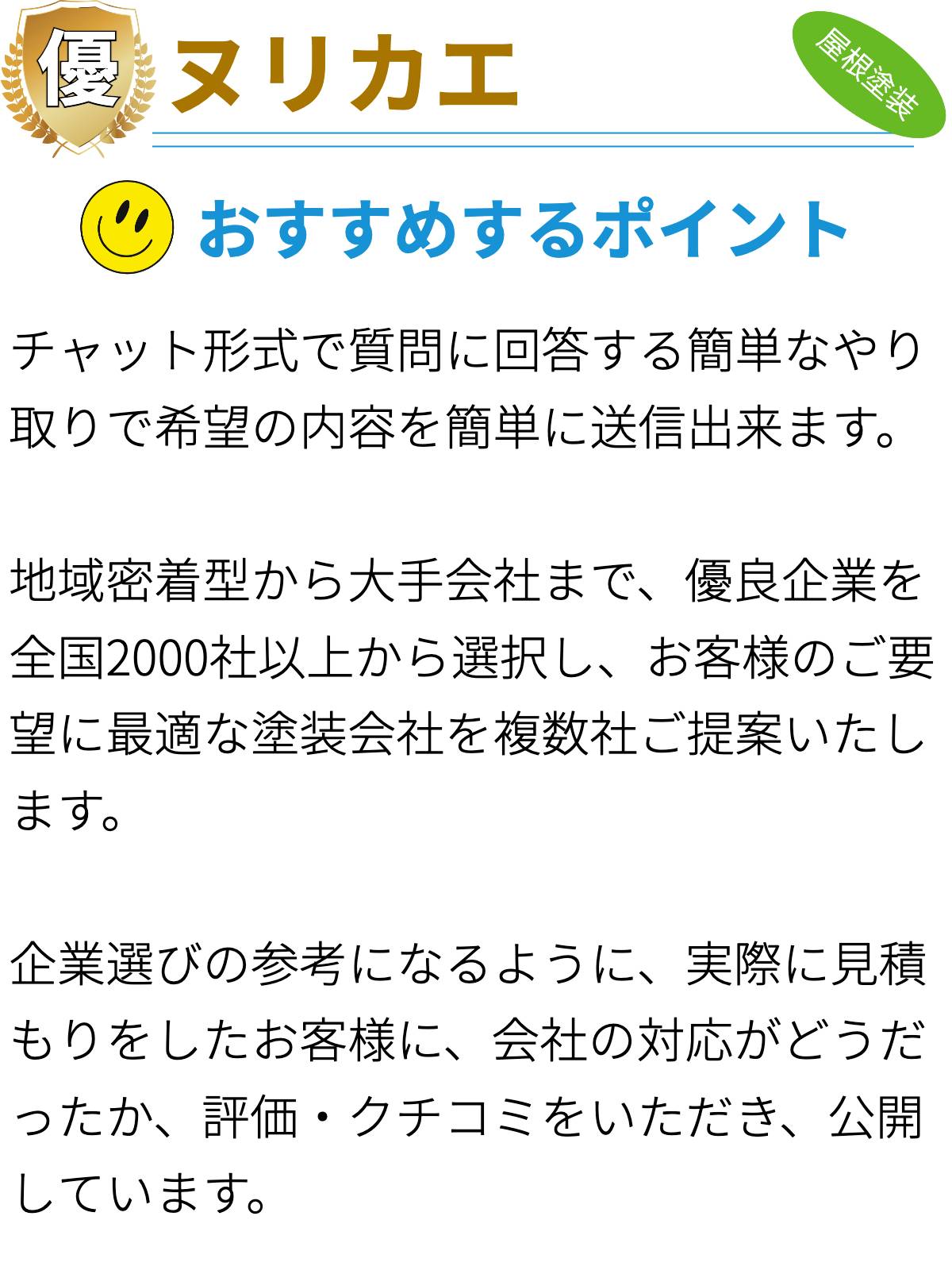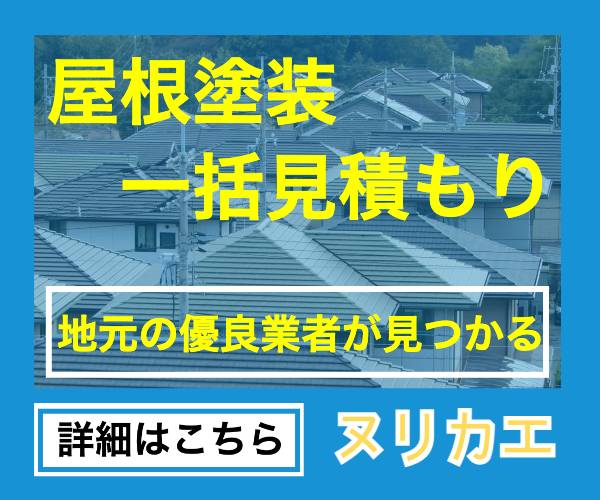#外壁塗装#屋根塗装#手抜き工事#されやすい
★手抜き工事されやすい工事について解説!★
職人社長 / 渡部が “外壁塗装” について語ります!
◇関連動画
■【公式】街のリフォーム屋さん WEBサイト
■電話番号
022-341-5508
■受付時間:10:00~17:00
※定休日:日曜・祝日
■質問・相談・お問い合わせは
もしくは フリーダイヤル 0120-341-853 まで!
■外壁塗装ショールーム
街のリフォーム屋さん (仙台泉本店)
宮城県仙台市泉区野村字新平山1-2 M-FACTORY 2F
■エリア
仙台、富谷、多賀城、名取、その他周辺部
(詳しいエリアについてはお問い合わせ下さい!)
屋根・外壁の無料診断も受付中!
下記URLから、24時間オンライン予約も可能です^^